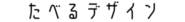50年後の未来へつなぐ、地域の食とは?
食は、風土と人の関係を未来へ繋ぐ手段
気候変動や人口減少、後継者不足など、日本各地で地域の暮らしが大きく変わろうとしています。
なかでも食文化はその土地らしさを映す大切な存在でありながら、日々の忙しさや社会の変化の中で、静かに姿を消しつつあるものの一つです。
地域の食材や料理、風習のひとつひとつには、その土地の気候や歴史、人々の営みが刻まれています。
けれど、今のままではそれらの多くが知っている人しか知らないまま、やがて消えていってしまうかもしれません。
だからこそ、「何をどう未来へ繋ぐか」という問いが、多くの地域にとって大きなテーマになっていると考えています。
大切なのは、特別なものを新しく生み出すことではありません。
むしろ、すでにその土地にある素材や料理、言葉や技術を、今の暮らしに合う形に“見直す”こと。
それをどう届ければ、次の世代に繋げるのかを考えることです。
たとえば、家庭では料理されなくなった食材や、昔の行事食など。
これらを「今」の生活に当てはめ考えなおし、「美味しそう」「作ってみよう」と思えるかたちに整えていくことが、未来へ繋ぐ第一歩になると考えています。
その為には、地域の中での繋がりがとても大切です。
生産者の思いを知ること、料理人の工夫にふれること、子どもたちが地元の味に親しむ機会をつくること。
一人ひとりの「食べる」という行為が、誰かの「作る」とつながり、地域の「繋ぐ」に変わっていきます。
食べるという行為は、ただお腹を満たすだけのものではありません。
誰が、どこで、なぜ作ったのか。
どうやって、誰と、なぜ食べるのか。
そんなことを考えてみることが、地域の文化を未来へ繋ぐ手段になります。
50年後の食卓に、今の「美味しい!」という笑顔がどれだけ残っているかどうかは、今を生きる私たちの手と選択に委ねられています。
一皿の中に、その土地の自然があり、人の手があり、暮らしがある。
食とは、土地と人の関係を未来へ繋ぐ手段です。
今ここで生まれる一皿が、遠く50年先の誰かの記憶になるのかもしれません。
たべるデザイン
上江田崇
たべるデザインへのご相談は初回無料です。
お気軽にお申し込み下さい。