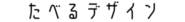地域の風土と人の手から生まれる、あたらしい価値をかたちに
何気ない日常のなかに、まだ言葉になっていない魅力が眠っています。
たとえば、手間を惜しまず作られる素材。
土地の歴史とともに育まれてきた食文化。
そして、その背景にある人の想いや営み。
私たちは、そうした地域の“まだ見ぬ魅力”に光をあてながら、商品やメニューの開発をお手伝いしています。
特に沖縄では、島野菜や近海魚、発酵文化など、独自の食資源が豊富に存在し、それらはただの「食材」ではなく、風土や人と深く結びついた「語るべき素材」でもあります。
けれど、魅力があることと、伝わるかたちにすることは別の話です。
どんな相手に届けたいのか。どんな体験として記憶に残したいのか。
言語化されていないその想いをすくい上げ、企画・レシピ・ビジュアル・ストーリーに丁寧に編みなおしていく。
それが、私たち「たべるデザイン」の仕事です。
商品開発やメニューづくりは、単なる“つくる”作業ではありません。
その土地に流れる時間や、そこに暮らす人たちとの対話からはじまる、いわば“関係性のデザイン”です。
沖縄という場所に限らず、地域の風土を活かした価値づくりを考えている方は、ぜひ一度ご相談ください。
あなたの手のなかにある素材や想いが、誰かの記憶に残るかたちへと生まれ変わるよう、私たちが伴走します。
未来につながる、”たべる”のデザインをサポートさせて下さい。
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。