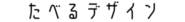人と食の間に“つながり”をつくるために
「デザイン」という言葉に、どんなイメージを持っていますか?
多くの人が思い浮かべるのは、ロゴやパッケージ、色や形の美しさかもしれません。
けれど私たちが考える「デザイン」は、少し違った場所から始まります。
それは、「食を通して、人と人、社会と地域の関係性をもう一度見つめ直すこと」。
つまり、目に見えるものだけでなく、目には見えない“つながり”や“背景”を整えていく営みそのものが、私たちにとっての「デザイン」です。
たとえば、
- 地域に余る規格外野菜を使って、心が温まるようなスープをつくる
- 受け継がれてきた伝統の味を、若い世代と一緒に再編集するレシピを考える
- 土地の香りを感じられるような、記憶に残る食体験をかたちにする
これらの営みはすべて、素材や風景の背後にある“意味”をていねいにすくい上げ、「誰かに届く形」に翻訳していくプロセスです。
伝える手段もまた、“食の一部”
料理や商品だけでなく、それを「どう届けるか」もまた、食の本質を左右します。
どんな写真で伝えるのか。どんな言葉で表現するのか。誰に向けて、どんな順番で届けるのか。
こうした細やかな設計が、受け取る人の印象や感情、行動さえも変えていきます。
だからこそ、私たちは「情報をどう届けるか」までを含めて、食のデザインだと考えています。
デザインとは、「問い直すこと」から始まる
私たちはいつも問いかけています。
「この料理は、なぜこの土地で生まれたのか?」
「この素材の良さは? どのような形であればそれが伝わるのか?」
「それは誰の、どんな時間をつくるのか?」
正解のない問いに向き合い、素材と土地、人と社会の間にある関係性をほどき、編み直す。
その過程で少しずつ「食のかたち」が見えてきます。
見た目だけでなく、“場”を整えるということ
食のデザインは、メニューやパッケージを考えることだけではありません。
そこには、誰がつくり、どんな想いで届け、どんな場面で食べられるかという“文脈”があります。
味や香り、手ざわり、空間、会話、余白──
それらすべてを含んで、ようやく「食体験」が成り立つのです。
だから私たちは、地域に根ざした商品を考えるときも、まずはその土地の人や営みに目を向けます。
何をつくるかよりも、「なぜつくるのか」から始めることを、大切にしています。
おわりに
食とは、栄養のことだけではありません。
それは土地の風景であり、誰かの記憶であり、文化そのものです。
私たちがめざしているのは、見た目の洗練だけではなく、食にまつわる“関係性”そのものをつなぎ合わせること。
そうして生まれた料理や商品が、誰かの暮らしの中に自然と根づき、また新たなつながりを生んでいく。
そんな循環の中にこそ、食の可能性があると信じています。
アイデア段階でも構いません。私たちたべるデザインにご相談下さい。